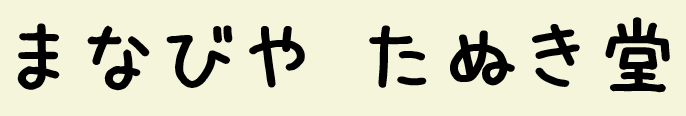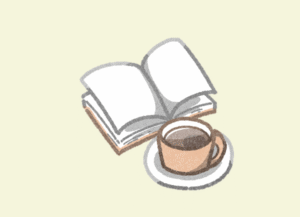ー判断力を身につけるー
迷っているときー
誰かの期待に揺れているときー
選ばなければならない場面に立ったときー
どうしたら正しい判断ができるんだろう。
「これでよかったのかな」と思うこともある。
「みんながそうしているから」と選んだ後に、どこか心がざわつくこともある。
“日々の選択に関する判断”
“仕事や責任に関する判断”
“自分の生き方に関する判断”
判断にはいろんな種類があるけど、正しさって、誰が決めるんだろう。
どうやって判断したらいいんだろう。
今日は、そんな問いについてゆっくりと考えてみたいと思います。
失敗しても自分で選ぶことが大事
判断するのは怖い。
もし間違えたらどうしよう。
誰かを困らせてしまったらどうしよう。
責められたらどうしよう。
そんな不安が、判断することをためらわせます。
誰かに決めてもらえば、失敗しても「自分のせいじゃない」と言える。
だから、判断を人に預けたくなることもあるかもしれません。
でも、それでも「自分で選ぶこと」を大切にしてほしいと思います。
なぜなら、たとえ迷っていても、たとえまだ未熟でも、自分で判断したことなら納得できるから。
他人が判断したことは、簡単に放り出せてしまう。
自分が納得して選んだ道であれば、最後まで守ろうと思える。
“正しい判断とは、自分の選んだ選択に納得すること”
難しい判断になればなるほど、他人に任せてしまいそうになるけど、小さな判断も、大きな判断も、私たち一人一人が自分で考えて、納得して選ぶことが、正しい判断をする一歩になるのです。
今の時代は、すでに多くが与えられています。
あらゆる物事が組織化されているから、自分が判断しなくても世の中はまわっていくし、それなりに生きていけます。
だけど世の中では、他人の判断に納得がいかずに怒っている人が増えていると感じます。
納得できない人は、他人がどんなにいい判断をしてもやっぱり納得できない。
だから、世の中がどんなに便利になっても、判断は自分でやらないと幸せにはなれない。
と私は思うのです。
判断力は、訓練で育つもの
「あの人は判断力がある」
そんなふうに見える人も、最初からそうだったわけではありません。
判断力は、訓練を積み重ねて育つもの。
つまり慣れの要素が大きいのです。
何度も判断を積み重ねることで、少しずつ判断することに慣れていく。
「こうすればよかった」と思った失敗も、その経験が、次の判断のときに背中を押してくれる。
判断力は、少しずつゆっくりと、でも確かに育っていくもの。
判断力は、特別な場面だけで使うものではなく、日々の中で静かに積み重ねていくものなのです。
だからこそ、迷っても、怖くても、「自分で選ぶ」ことをやめないでほしいのです。
判断力を見につける訓練は、難しいものではありません。
小さなことから、少しずつはじめられます。
たとえば、今日傘を持っていくか持って行かないかを選ぶことも、ひとつの判断。
これはあまり難しくない。
でも、「自分で選ぶ」という感覚を育てるには、十分な訓練になります。
次は、もう少しだけ迷う場面。
たとえば、誰かに声をかけるかどうか。
たとえば、仕事でどちらの案を提案するか。
そうやって少しずつ、判断のハードルを上げていく。
それを何度も繰り返すうちに、選ぶ力が育っていきます。
段々と自分にとって正しい判断ができるようになってくるのです。
判断の軸 ─何のために、誰のために
判断に迷ったときは、「何のためにそれをするのか」を思い出す。
「誰のために、その選択をしようとしているのか」を問い直す。
その問いが、静かに自分を支えてくれる。
「みんながやってるから」「普通はこうするから」
そんな言葉に、流されそうになるかもしれません。
でも、誰かにとって正しいことが、自分にとっても正しいとは限らない。
たとえば、誰かが「それは間違ってる」と言ったとしても、自分の中にある軸が「これが必要だ」と感じているなら、その判断は、きっと自分にとっての正しさになるのです。
逆に、誰かの正しさに乗ってしまうと、あとで迷いが残ることがある。
「本当は、違う選択をしたかったかもしれない」と。
だからこそ、正しい判断の第一歩は、ちゃんと自分で考えること。
自分の軸で、静かに問い直すことが大切なのです。
正しさは、あとから育つこともある
判断したときには、不安があるかもしれない。
「これでよかったのかな」と思うこともある。
でも、自分でちゃんと考えて判断したのであれば、その判断が最善なのです。
だから、その判断をした自分を責める必要はありません。
完璧な判断を求めすぎず、その時、最善の判断をしたと納得できることが大事です。
それから、判断はすぐに結果がでないこともある。
最初のうちは間違っていたかもと思っても、あとから「これでよかった」と思えることもあります。
だから、自分の判断の結果に一喜一憂せず、誠実に決めたことを続けてください。
あなたの判断が、みんなの灯りになる
誰しも、判断するのは怖い。
だからこそ、判断する人はまわりの指針となる重要な存在になります。
あなたが判断することで、
「あの人が選んだから、自分も選んでみよう」
「あの人が迷いながら進んでいるなら、自分も進んでいいのかもしれない」
と思う人がいます。
あなたが「それでも、これを選ぶ」と言ったとき、その姿に励まされる人がいます。
判断する人は、声を張り上げなくても、その存在だけで、誰かの灯りになる。
あなたが自分で選ぶことは、誰かの灯りになるかもしれないのです。
そして、またその誰かの灯りが、次の灯りをともしていきます。
おわりに ─「正しい判断ができる」とは
「どうしたら正しい判断ができる?」
その問いに、たぬき堂として答えるなら、
正しい判断とは、「自分の軸で考え、経験を積み重ね、その判断に納得できること」。
納得があれば、その判断が上手くいっても失敗しても、その過程や結果がすべて学びになります。
そして、それがあなたにとっての正しい判断となるのです。
だから、今日のあなたの選択を、どうか信じてあげてください。
その判断は、きっとあなたの歩みを支えてくれます。
そして、誰かの夜に、そっと灯りをともすこともあるでしょう。