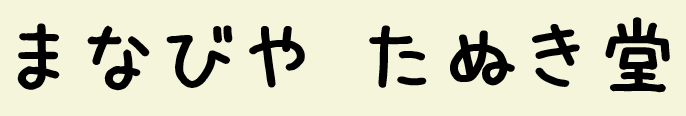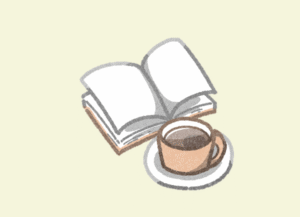─物価高の時代に、支援のかたちを考えるー
こんにちは。まなびや たぬき堂のたぬきです。
最近、物価がじわじわと上がっていて、暮らしの中で「前より高くなったな…」と感じることが増えてきました。
そんな中、政府の対策として「”減税”と”給付金”、どちらがいいの?」という話をテレビなどで聞くことがあります。
「一体どっちがいいんだろう?」
「お金のことって難しい、、」
そこで今回は、”物価高対策”という前提で、減税と給付金の違いを、静かに考えてみたいと思います。
給付金の良さ──必要な人に、ピンポイントで届く支え
まずは、給付金について。
給付金の最大の特徴は、「直接、現金が届くこと」です。
最近では、マイナンバーと口座の紐づけが進み、手続きもずいぶん簡素化されてきました。
たとえば、住民税非課税世帯や子育て世帯など、生活に余裕がない人にピンポイントで届けることができる。
これは、物価高のような“生活に直結する困難”に対して、即効性のある支援になります。
「もらえた」という安心感は、心の余裕にもつながります。
それは、数字では測れないけれど、確かに暮らしの中に灯るものです。
減税の良さ──じわじわ効く、静かな支え
一方、減税は「取られなかった」というかたちで、支援が届きます。
たとえば、消費税を下げれば、毎日の買い物の中で少しずつ負担が軽くなる。
それは、給付金のような“目に見える支援”ではないけれど、じわじわと効いてくる支えです。
特に、長期的に行うなら、減税は生活の底を支える力になります。
ただし、減税は所得に関係なく一律で行われるため、高所得層にも恩恵が出てしまうという側面があります。
結果として、支援の効果が分散し、「本当に困っている人」への支えが薄まってしまうこともあります。
支援の目的と経済状況による違い
支援のかたちは、「何のために行うか」で意味が変わります。
今回のように”物価高対策”という目的があるなら、支援は“生活が苦しい人”に届くべきです。
以下に、目的と経済状況による支援の向き不向きを整理してみます。
| 支援の目的/状況 | 一律減税 | 給付金(ピンポイント) |
| デフレ(物価下落) | ✅ 消費を促し、景気を刺激できる | △ 一時的な効果にとどまりやすい |
| インフレ(物価上昇) | ❌ 消費を刺激しすぎて、物価上昇を加速する可能性 | ✅ 困っている層に集中できるため、物価への影響が抑えられる |
| 景気刺激(消費促進) | ✅ 継続的な消費を促す | △ 一時的な消費にとどまりやすい |
| 生活支援(物価高対策) | △ 高所得層にも恩恵が出るため効果が分散 | ✅ 所得に応じた支援が可能で、即効性もある |
| 所得格差の是正 | ❌ 一律減税では格差が広がる可能性 | ✅ 必要な人に集中できる支援が可能 |
この表からもわかるように、物価高対策としては、給付金の方が理にかなっていると言えそうです。
心理の話─「もらう」より「取られない」方が印象に残る
支援のかたちには、経済的な効果だけでなく、心理的な受け取り方の違いもあります。
行動経済学では、「損失回避(loss aversion)」という心理が知られています。
人は、同じ金額でも「得をする」より「損をする」方が約2倍強く反応する──というものです。
つまり、1万円もらったときの嬉しさより、1万円取られなかったときの安心感の方が強く残る。
この心理が、減税の方が「ありがたく感じる」理由のひとつになっています。
給付金は「得した」感覚があるけれど、印象は一時的になりがち。
減税は「取られなかった」安心感がじわじわ残るため、好まれやすい。
でも、心理的な納得感と、支援の必要性は、必ずしも一致しない。
だからこそ、支援のかたちを考えるときには、「心にどう届くか」だけでなく、「誰に届くか」も見つめる必要があります。
支援の線引きと、納得のむずかしさ
給付金のように、所得や世帯状況によって支援の対象を絞ると、どうしても「線引き」が生まれます。
そして、その線引きには、不満や疑問もついてきます。
「働いてない人に支援が届くのは納得できない」
「自分は共働きでギリギリなのに、対象外になるのはおかしい」
「資産があるのに収入が少ない人がもらえるのは不公平」
そんな声が出るのも、自然なことです。
実際、非課税=困っているとは限らないし、年収1000万円でも苦しいと感じる人もいます。
人それぞれ、生活スタイルも価値観も違う。お金の感覚も違う。
だからこそ、支援の線引きには、納得のむずかしさがつきまといます。
でも、わたしはこう思うのです。
納得できない気持ちがあることも、ちゃんと受け止めたい。
そのうえで、「誰かが救われるなら、それでいい」と思える社会の空気を、少しずつ育てていけたらとー。
たぬき堂の視点 ─やさしさのかたちを問い直す
支援は、制度でありながら、誰かの生活に寄り添うものです。
だからこそ、損得や公平感だけでなく、「必要性」と「やさしさ」で考えたい。
一律の減税は、広く恩恵があるように見えて、困っている人ほど“支援の薄さ”を感じてしまう。
一方、ピンポイントの給付金は、「線引きがある」ことで不満も生まれやすいけれど、支援の本来の目的──“必要な人に届くこと”──には忠実です。
そして、今はマイナンバーと口座の紐づけが進んでいる。
技術的にも、やさしさの精度を高めることができる時代になってきています。
だからこそ、支援のかたちは「誰に届くか」「どう届くか」を、もっと丁寧に見つめ直してもいいのではないでしょうか。
支援は、ただ「配る」ものではなく、“届き方の誠実さ”が問われるもの。
それが、たぬき堂の灯りのような、静かであたたかな支え方だと思うのです。
おわりに 支援は、心に届く灯りであってほしい
「減税と給付金、どちらがいい?」という問いには、正解はありません。
それぞれに意味があり、それぞれに届き方がある。
でも、今回のように「物価高で苦しんでいる人を支える」という目的があるなら──
支援は、必要な人に、静かに、確実に届いてほしい。
そして、たぬき堂ではこう願います。
支援のかたちが、損得や効率だけで決まるのではなく、やさしさと必要性で整えられる社会でありますように。
納得できない気持ちがあることも、ちゃんと受け止めながら、
「誰かが救われるなら、それでいい」と思える空気を、少しずつ育てていけたら──
今日も、たぬき堂はここにいます。
誰かの「助けてほしい」に、静かに寄り添える灯りでありますように。